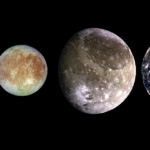Mariamichelle / Pixabay
ミラノからユーロスターで2時間半、古都フィレンツェにつく。
古都というからには、古いものを手つかずで置いておこうというのであるから、近代的なインフラ整備を期待してはならない。
水道の水の出が悪いなどと苦情を言ってはいけないのである。
それにしても、かつて中世のヨーロッパ世界を、鮮烈な色彩で塗り替えた衝撃の都である。
アルノ川沿いのホテルの窓からヴェッキオ橋を望むと、ルネッサンスをリードしたメディチ家の威風をひしと感じる。
ルネッサンスは、長年ヨーロッパ世界に覆いかぶさってきたローマ教会の圧力に抗って生じた爆発といえる。
14世紀、足利尊氏が室町幕府を開いたころ、中世ヨーロッパでは迷信がはびこり、占星術、魔術、魔女裁判が横行し、ペストが大流行して4人に一人が命を落とした。
ヨーロッパはどんより曇って、不穏である。
唯一、救いをイエスキリストに求めるしかない状態であった。
すがるものにとって、この世は主の御心のままにあり、教会の声は絶対である。
ひとは神のしもべであって、聖書の教えに逆らってはならない。
信じることが大切で、個人が自分で考えてはならないのである。
この世は原罪をつぐない、救われるために準備をするところであるとされた。
皮肉なことだが、ローマ教皇が音頭を取った十字軍の遠征は成果が上がらず、ローマ教会の権威は衰退した。
その反面、ビザンツ帝国、イスラム圏との貿易は活発になった。
14世紀半ば、荘園領主に搾取される一方であった農民のなかから、手工業者や商人に転じて都市に住みつくものが現われた。
とくにイタリア北部の都市では毛織物や地中海貿易で財を成すものが続出した。
その代表がフィレンツェ商人である。
成功の秘訣は、他に先んじて情報を入手することで商業、金融の世界を制したことである。
彼らは「実際に目で見たものしか信用してはならない」、「神は努力しているものしか助けてくれない」、「今日できることは明日に延ばすな」と、自ら体験したことを家訓として、それを我が家の門前に堂々と掲げた。
その生き方はひたすら信じるという中世的観念から脱し、自分の目だけを頼りに判断するという新時代の強い意志の表明であった。
彼らは煩わしい教義にとらわれず、人間的で自由な生き方を模索するようになった。
その結果、古代のギリシア・ローマ時代に素晴らしい文化が花開いていたことを発見したのである。
驚くべきことだが、1000年以上にわたってギリシア・ローマ文化は歴史の闇に埋もれたままになっていたのである。
当時はキリストの出現以前であるから、当然ながら教会の説教はない。
ひとは心ゆくまで自由を謳歌し、人生を楽しんでいるではないか。
カトリックで覆い隠されていた個人がここでは主役を演じている。
絵や彫刻をみても、描かれているのは偶像化された聖人ではなく、見たままの人の姿である。
ローマ教会を離れてみると、こんなにも美しく喜びに満ちた世界があったのかという感激が、彼らの間にふつふつと湧いてきた。
人生は神のためにあるのではない。
われわれ人間こそ主役であるという発見である。
当時の芸術家、思想家、科学者の多くがその気分に啓発され、自由で人間的な作品、研究成果をものしたのである。
イタリア一国に限っても、ダ・ビンチ、ミケランジェロ、ラファエロなどの芸術家、ダンテ、ボッカチオなどの作家、天文、物理学者ガリレオ・ガリレイ、政治学者マキャベリ、建築家ブルネッレスキなど枚挙にいとまがない。
こうしてフィレンツェ、ミラノ、ヴェネツィアなど自由都市の豪商にとっては、これらの画家、彫刻家、建築家のパトロンとなって、彼らの芸術品を蒐集することが一流のステータスとなった。
ダ・ヴィンチとミケランジェロがルネッサンスを代表する芸術家であることは今さら言を俟たない。
ただ、同郷でありながら二人が一緒にいたのはわずか5年間である。
ふたりは互いに意識しあいながら、自らの優位を主張した。
ダ・ヴィンチは「絵画論」のなかで、絵画がすべての学問、芸術にまさるといったが、ミケランジェロはみずから彫刻家であることを自負し、絵画の依頼にはしぶしぶ応じるという具合であった。
いずれにしても、ふたりの多方面にわたる業績は余人の追随を許さない。
ともに決して恵まれた環境で修業したわけではなく、天賦の才としかいいようがない。
ダ・ヴィンチは筆が遅く、完成に至らなかった作品が横溢しているが、それにも拘わらず見事な出来栄えなのである。
一方ミケランジェロはいったん仕事を始めると進行はきわめて早く、一気にやり遂げるタイプであった。
しかしどちらも、目で見たものだけを表現するという気分に溢れていた。
20歳のダ・ヴィンチが描いた「受胎告知」は天使もマリアも普通の人間と変わらぬ姿で描かれ、周囲を驚かせた。
その後ミラノで依頼された祭壇画では、教会の反発を押し切って聖人から金の光輪を取り除いた。
そして「最後の晩餐」ではついにキリストの頭上からも光輪を消してしまった。
彼は圧力に屈することなく、生身の人間を描くことに固執したといえる。
一方ミケランジェロはローマ教皇ユリウス2世から、システィーナ礼拝堂の天井に12使徒を描くよう命令されたが、これを無視して創世記をテーマにした『天地創造』を制作した。
さらに20年後にはパウルス3世からシスティーナ礼拝堂の壁に『最期の審判』を描くよう命じられたが、登場人物のほとんどを全裸で描き、教皇をあわてさせた。
ローマ教皇の権威にも屈しない芸術へのこだわりを示すエピソードである。
こうしてルネッサンスはカトリック世界から個人を解放したが、いいことばかりではなかった。
人生を謳歌しすぎると、生活は華美となり、節度を失って退廃的となる。
これに危機感を覚えたサンマルコ修道院の院長サヴォナローラは、信心深く清貧な生き方を説いて市民に警鐘を鳴らしたため、あおられていた火は鎮火に向かった。
さらに当時のイタリア諸都市はそれぞれが独立国家の風を呈していた。
そこへ目を付けたフランスや神聖ローマ帝国が、領土拡張を目指してイタリアへ侵入し、50年にわたって戦闘を繰り返したためフィレンツェは疲弊した。
そして18世紀に入ってメディチ家の継承が途絶えると、ついにフィレンツェはオーストリアのハプスブルク家に支配されることとなった。
ルネサンスもそれに引き続きおこった宗教改革も、ともに古代への復古運動という点で共通している。
ただ宗教改革がひたすら人間の無力さを見つめていて、いかにも暗いのに対し、ルネサンスは人間性が解き放たれた歓喜のなかで、ひとびとが光り輝いてみえる。
しかもその輝きは、今なおフィレンツェのあちこちに見ることができる。
世界中からこの街を訪れるひとが絶えないのも、わけあってのことであると納得した。