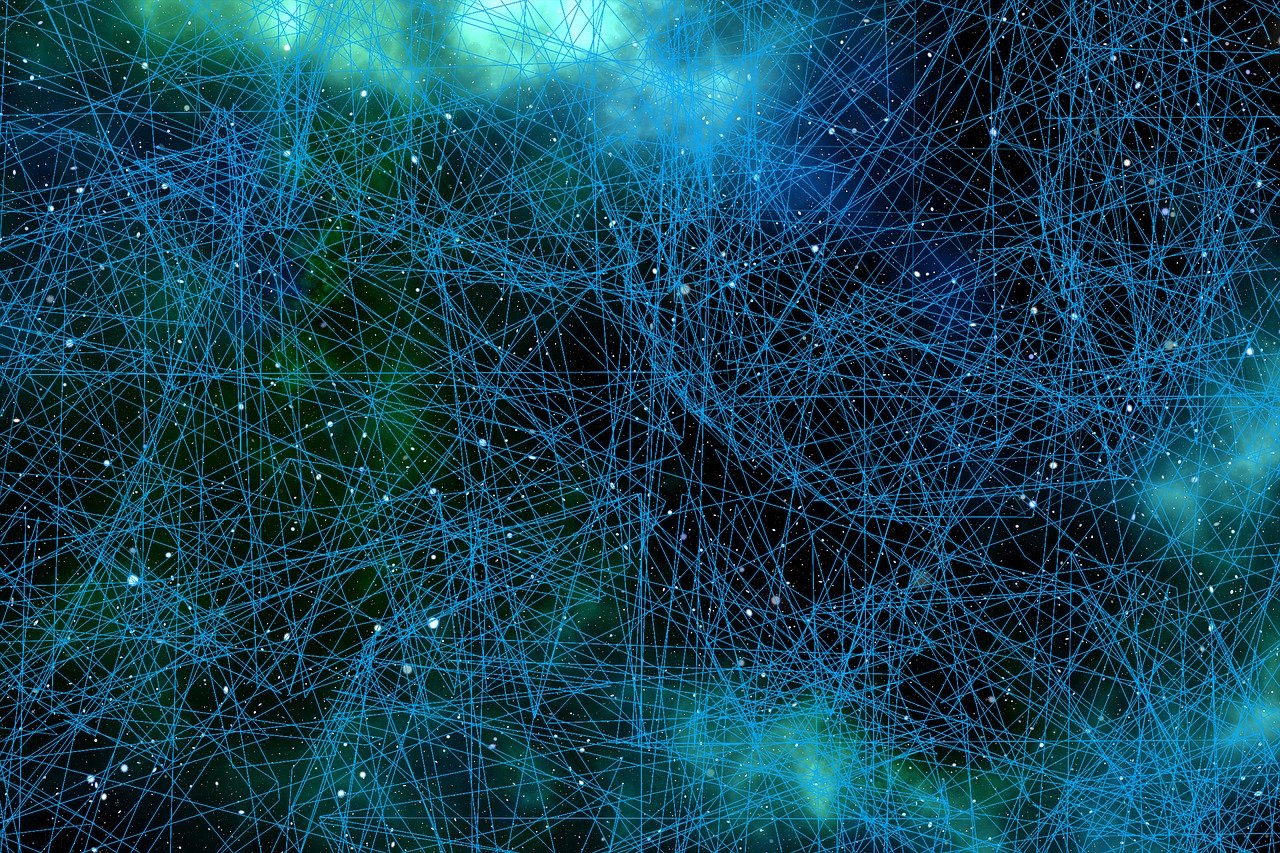
geralt / Pixabay
刺激のない田舎町にいて、なんとなくその日を過ごしているだけの高校生にとって、いきなり文系理系のどちらに行くのかと言われても、確固たる信念などないものが多かった。教師より、ヨーロッパの同年代の子は、すでに職業を意識した専門分野に進学していると聞き、驚いた記憶がある。
そんなとき、偶然、文系大学教授の講演を聞く機会があった。初めて見る「大学教授」は崇高で、仰ぎ見る巨人という印象であった。はなしは「デカルトの生き方」についてであった。
3代将軍・徳川家光と同時代の人で、「我思うゆえに我あり」で有名な哲学者だ。
「若い君たちは進路を迷うことが多いだろう。しかし、時期至れば否応なしにAかBかを決めねばならない。Aといったん決めたら、後ろを振り返ってはならない。もしBにしておけばどうだったかということは考えてはならない。」
そんな話しだった。デカルトというひとも、そういう人生の悩みを持っていたんだと、妙に納得したものだった。
それから50年が過ぎて、たまたまデカルトの「方法序説」を手にする機会があった。あのときの話しがどう書いてあるのか、気もそぞろに紐解いてみた。
我思うゆえに我あり
「方法序説」はデカルト41歳の著作であるが、彼はそれまで20年にわたって、真理を確実に認識するため、身の周りのすべての事象を疑ってかかるという忍耐強い作業をおこなっていた。
その結果、この世の中に、なにひとつ確かなものはないけれど、それを疑っている自分の頭の中、理性だけは信じるに足ると結論づけたのであった。
私とは「思惟するもの」であり、これこそが絶対確実な学問の基礎をなす、第一原理であると位置づけた。
「我思うゆえに我あり」はその作業から導かれた結論である。
これほど練りに練った結論であったが、のちに汎神論者のスピノザは、「我思う」と「我あり」は「ゆえに」でつながるのではなく、対等の関係であると論及し、また後世に至りフロイトは、「我思わなくても我あり」といって無意識の世界観を明らかにした。
さらにラッセルは、「我思う」を単なる意識内容の告知とみなし、「I think therefore I am」を「It think within me」と表現し、デカルト理論に一石を投じた。それほどにデカルトは哲学を志向するものにとって、避けて通れない存在であったといえる。
「方法序説」第3部
気になる著述は「方法序説」第3部に出ていた。
そのなかで、デカルトは人が幸福に生きるためにどういう規則を自らに課すべきかを思索し、三つの提言をしている。
一つ目は、法律と習慣とに服従し、神の恩寵により幼児から教えこまれた宗教をしっかりと持ち続け、そのほかは最も分別ある人々による最も穏健な意見に従うこととした。(彼はスコラ哲学に基づくキリスト教とは決別したが、決して無神論者ではなく、神の存在証明すらおこなっている。)
二つ目は、自分の態度をあいまいにせず、きっぱりした行動をとること。いかに疑わしい意見でも、一旦それと決心した場合は、変わらぬ態度で従い続けるのがよい。
あちこち迷い歩くべきではなく、いわんやそこに留まるのでもなく、同じ方向に真っ直ぐ進むべきである。
仮にその選択が単なる偶然にすぎなかったにしても、少々の理由では方向を変えるべきではない。そうすることによって、望みどおりの場所でなくても、どこかには辿りつき、それは恐らく森の真ん中よりは良い場所であると思うからである。
まさにこの部分が、学生のころ興奮をもって聞き入った個所である。
実際にデカルトの著述をこの目で確かめることができ、なんだかほっとした気分になった。
現在、デカルトの頃とは比較にならぬほど情報が溢れているとはいえ、今も、しばしば人生の選択を迫られることに変わりはない。したがって、デカルトの箴言はいささかも色褪せてはいないと感じた。
当時を懐かしみながら、書斎で執筆に明け暮れるデカルトを身近に感じたことであった。
ちなみに三つ目は、うまくいかなくても運命と諦めず克己に努め、欲望を抑えて、本来あるべき方向へ進路を変えるよう努めること。そして最善の努力を尽くしても不首尾に終わった場合は、もともと自分には無理であったと自らを納得させることが大切であるとした。
「方法序説」の出版
この書のなかで、彼は信仰によってのみ真理に到達できる(神が真理を照らし出す)というスコラ哲学を否定し、理性でもって考え抜けば理に叶った着地点があるはずで、すべては神の教えでなく私たち自身が決めることだという考えを示した。それは中世を支配する宗教界に対する挑戦状である。公表すれば命の保証はない。
彼は「方法序説」を出すにあたり親友の神父・メルセンヌに草稿の点検を依頼した。そして、匿名で出版すること、もし露見しても命を狙われないように、宗教批判の表現をカムフラージュして曖昧にし、学術書でないと思わせるために、わざわざラテン語でなくフランス語で書くようアドバイスを受け、これに従った。
4年前にはガリレオが地動説を唱え、ローマの異端審問所から地動説の破棄を強要される事件が起こっており、危険を覚悟の出版であったが、時代の転換にあたって既存勢力との軋轢は避けがたい。
正しいのは、神ではない。理に叶うことが正しいとする「方法序説」は、近代合理主義の発露となり、中世を終わらせる切り札という歴史的著作となったのであった。

