自家製麻酔薬
今から200年ほどさかのぼる1804年のことである。
紀州の田舎の一開業医が自家製麻酔薬を使って、世界で始めて乳がんの手術を成功させた。
失敗すれば殺人罪に問われかねない瀬戸際でメスをもち、果敢に手術に挑んだのである。
この金字塔が独学の一医家によってうち建てられたところに意義がある。
なにしろほとんど臨床経験のない無名の医者が、メスで切っても痛みを感じなくする薬を開発するという、容易に信じられぬはなしである。
彼の新薬開発はこのありえない世界のはなしである。
いまなら薬理学者と臨床医が研究チームを組んで、薬理作用の研究と平行して動物実験から臨床実験にはいるのであるが、彼には、相談すべき共同研究者がおらず、文献もなく、独自で研究をすすめなければならなかった。
たとえ開発した薬に効果があったとしても、
など、膨大な医学的知識とチームを組んだ大規模な臨床試験が不可欠である。
23歳で上京した彼の医学研修は3年であったが、わずか3ヶ月の漢方医学研修と1年間のオランダ流外科学修行が主たるものであった。
すでに上京前から中国の麻酔医華陀にあこがれていたというが、修行中、若い青洲にとって衝撃的な体験があったのであろう、帰郷時にはすでに今後の生き方を決定している。
この間、京の整体師がマンダラゲやトリカブトの抽出液を治療に用いているのを見聞し、帰郷後ほどなく自宅の庭で栽培した薬草を組み合わせ、手術に堪える麻酔薬の研究にとりかかった。
おそらく彼は京での修行中、麻酔こそ外科医にとって不可欠の武器であると痛感し、その開発を一生の仕事にするべく決心したものと思われる。
わずかなオランダの医学書しか入手できなかった時代に、田舎で開業医をしながら、いったい彼はどのようにして研究者に変身していったのであろうか。
遅々として進まぬ研究に茫然とする日々が続いたことは容易に推測される。
今の世でも、実験の成果が理屈どおりに出ないことは、ほとんどの研究者が実感するところである。
自宅周辺に埋められた夥しい動物実験の犠牲者(犬・猫)に、世間から不審者のレッテルを貼られながらも、”持続こそ力である“と自らに言い聞かせつつ、20年間ともかく彼は研究を続けたのである。
ガスの吸入や注射なら短時間の麻酔も可能であるが、当時は飲むしか方法がなく、いったん麻酔すると容易に覚めにくいため危険は大きかった。
さらにこれを実用化するには、ひとで試さなければ効果の程は分からない。
麻酔実験の最終段階に到り、彼はついに家族の生死を賭けてまで臨床実験にとりかかっていく。
麻酔量を決定するための実験は、何度も繰り返しおこなわれたはずである。
このくだりは有吉佐和子の能筆に十二分うかがわれるが、そこまで彼をつき動かした情熱はもはや情念というべきであろう。
ところで、乳がんのことである。
そもそも乳房は婦人の急所とされ、傷つければ死ぬといわれた時代である。
が偶然、牛の角で乳房を突き刺された婦人の手術をしたところ、みるみるよくなったのに自信をもった彼は、ついに意を決して乳がん摘出術に挑むこととなる。
胸の高鳴りを抑えながら、メスを握る青洲の姿が髣髴として目に浮かぶ。
麻酔が効きすぎて死亡すれば殺人罪に問われるかもしれず、後世に名を残すどころか罪人の汚名を着せられるかもしれぬ。
失敗が許されない極度の緊張下で、見事に彼は試練を制し、一躍時の人となった。
彼は75で世を去るまで、153例の乳がん手術を手がけ、諸藩から詰め掛けた1000人をこえる弟子を養成したという。
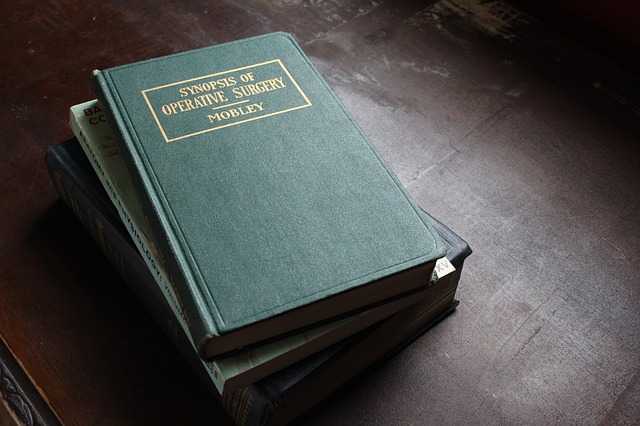
ただ彼は乳がん患者の治療記録を残したが、著作は残さなかった。
彼は手術の場に弟子を立ち会わせ、助手をさせながら手技を体得させた。
そして免許皆伝としたあとは、他人にその手技を教えてはならないとする誓約書を書かせ門外不出とした。
弟子は全国に散って家業を繁栄させたであろうが、それ以上の広がりはなかったといえる。
自分の手技が誤って伝播するのを恐れた青洲の心情は推し量ってあまりある。
だが彼の秘密主義は、同時代人である洪庵の情報公開主義と対比され、後世、世の批判にさらされることとなった。
けだし名声は泡沫のごとしである。

