 平安時代
平安時代 藤原泰衡の苦悩
100年続いた奥州藤原氏最後の当主・泰衡を評価したい。1189年、頼朝の攻撃を受けた彼は、平泉に陣をしかず、北へ逃走した。通常、強大な相手に攻められた場合は、堀や土塁を築き、館にこもって、焦土作戦をとるのが普通だが、彼はそれをしなかった。彼...

 平安時代
平安時代  戦国時代
戦国時代 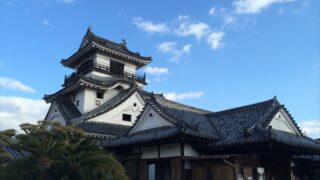 幕末
幕末  戦国時代
戦国時代  明治
明治  幕末
幕末  明治
明治  幕末
幕末  明治
明治  明治
明治  幕末
幕末  平安時代
平安時代