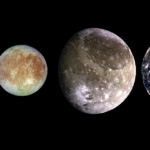釜石に友人がいる。今度の大地震のあとやっと電話が通じると、津波で自宅の診療所は壊滅したが、幸い命拾いしたよと明るく言う。
釜石市は山に向かってゆるやかな斜面をなしていて、今回海に近い街の半分が消失したそうだ。彼の家もそこにあった。
学生時代、仲が良かったので、釜石には何度も足を運んだ。盆正月になると臆面もなく出かけ、居座っていたが、居心地はすこぶる良かった。
要するに招かれざる客にも、家族ぐるみで歓待するのが家風とおもえた。親友の父は清廉な医師で、金銭に無頓着で身ぎれいだった。
仕事を楽しんでいて、しょうがないなと言いながら時間外の診療も嫌がっている風はなかった。医師の家としてはこじんまりとして、当時、風呂も近くの銭湯に通うのを潔しとしていた。
米沢藩の藩医の家柄で10何代目かにあたると、ひとから聞いたことがある。夕食になると皆でちゃぶ台のまわりを囲み、私はたちまち家族の一員となった。
親父さんはさりげなく奥さんに、「若い人へ食べさせてあげなさい」と言って、自分の分を回してくれるひとだった。口数が少なく、仏頂面して若者の話しを聞いているが、時々はにかむように笑うのが印象的だった。
その後、大病を得て、不本意な晩年を過ごされた。医療ミスで致命傷に至った疑いがもたれたが、一言も愚痴はこぼされなかったと聞く。
やはりなと思った。息子もよく似ていた。子供のころから、夏になると近所の主婦に頼まれ、年少の子供たちを海水浴に連れて行くのが日課であったと聞く。
子供たちが泳ぎ疲れると、全員を連れて帰り親元へ届けた。自分は終日、炎天下の砂上に坐っているだけである。それを格別不満とも思わないんですよと、かつて彼の母親が笑って話してくれた。
学生時代、深夜腹が減ると、彼のうちへ出かけた。「何かないか?」というと、すでに準備していたかのように、ト-ストを焼いたり、紅茶を入れて小腹を満たしてくれるのである。
無論無償なのだが、彼はもてなすことを楽しんでいるようにみえた。自分に限らず、友人の多くが腹をすかして出入りしていた。
「奇特なやつだ」といいながら、仲間の誰もが彼を頼りにした。地震のあと1週間は音信不通だった。
津波で自宅は崩壊したが、難を逃れた県立病院に出向いて、被災者の救助に当たっていたらしい。
遠方から医療スタッフが来てくれて、やっと解放されたという。500人もの死者が出たから、死体処理と病人の診療で、寝る暇がなかったらしい。
電気、水道、ガスがないと、さぞかし不自由だろうと同情するのだが、なあに夜が明けたら起きて、暗くなったら寝るだけさという。
仙台にいる子供たちから、避難して来いと言われているらしいが、行けるわけがないという。
「耳鼻科の医者は俺しかいないんだ。」自信にあふれた言葉だった。
これから仮設診療所を開くために忙しいんだということだった。電話のあと、「ノブレス・オブリージュ」という言葉が頭に浮かんだ。
ヨーロッパ社会にみられる、社会的に責任ある地位にあるものはそれ相応の義務を負うべきであるという不文律である。ただ金を出せばよいというものではない。
他国との戦争になれば先頭に立って、命を張るというほどの心意気である。それをいやいやでなく、率先してするところに彼らのプライドがある。
学生時代から一貫して変わらぬ彼の姿勢は、このヨーロッパの慣習を彷彿とさせた。
彼の「無私」は親を見て育ったからか、遺伝なのかなどと思いを巡らせていると、どうも昔から彼に弄ばれていたような気分になった。