 興味深い日本人
興味深い日本人 西行の旅
愁眉の急 ”大仏殿復元”69歳の西行に勧進のため奥州へ旅立ってくれと言ったのは、東大寺造営責任者の重源である。時は平安末期の1186年である。そのころ西行は伊勢にいて、地元の神官たちに和歌の指導をしている隠者であり、当時69といえば、ほぼ寿...
 興味深い日本人
興味深い日本人  興味深い日本人
興味深い日本人  興味深い日本人
興味深い日本人  興味深い日本人
興味深い日本人 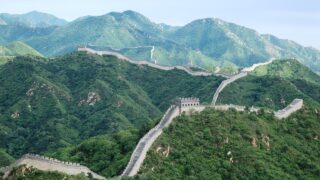 世界史ひとこま
世界史ひとこま  世界史ひとこま
世界史ひとこま 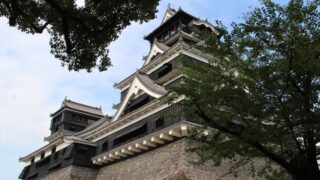 江戸時代
江戸時代  医学史ひとこま
医学史ひとこま  戦国時代
戦国時代  世界史ひとこま
世界史ひとこま  日本人気質
日本人気質  日本人気質
日本人気質  戦国時代
戦国時代  室町時代
室町時代  古代
古代  古代
古代  興味深い日本人
興味深い日本人  明治
明治  記憶に残る伊予人
記憶に残る伊予人  古代
古代  興味深い日本人
興味深い日本人  幕末
幕末  日本人の宗教心
日本人の宗教心  四季雑感
四季雑感  興味深い日本人
興味深い日本人