 日本人風雅考
日本人風雅考 数寄(すき)
歌道の風流数寄は風流・風雅に心を寄せることをいい、鎌倉時代に入り、歌道の風流を意味するようになった。それを体現したひとに西行がいる。家族を捨て歌道の道に没入した西行に、世間は憧憬と賞賛を惜しまなかったため、後世、彼に続こうとするものが絶えな...
日本人にみられる特有の風雅のこころを採り上げてみます。

 日本人風雅考
日本人風雅考  日本人風雅考
日本人風雅考  日本人気質
日本人気質  興味深い日本人
興味深い日本人  古代
古代  医学史ひとこま
医学史ひとこま  日本人気質
日本人気質  医学史ひとこま
医学史ひとこま  日本人風雅考
日本人風雅考  日本人の宗教心
日本人の宗教心  日本人の宗教心
日本人の宗教心  興味深い日本人
興味深い日本人  江戸時代
江戸時代  医学史ひとこま
医学史ひとこま  医学史ひとこま
医学史ひとこま  平安時代
平安時代  日本人の宗教心
日本人の宗教心  日本人気質
日本人気質  日本人風雅考
日本人風雅考  日本人気質
日本人気質  日本人風雅考
日本人風雅考  日本人風雅考
日本人風雅考 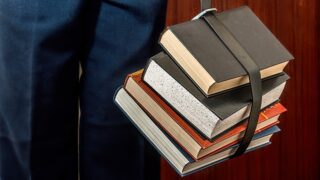 日本人気質
日本人気質  日本人気質
日本人気質  日本人の宗教心
日本人の宗教心